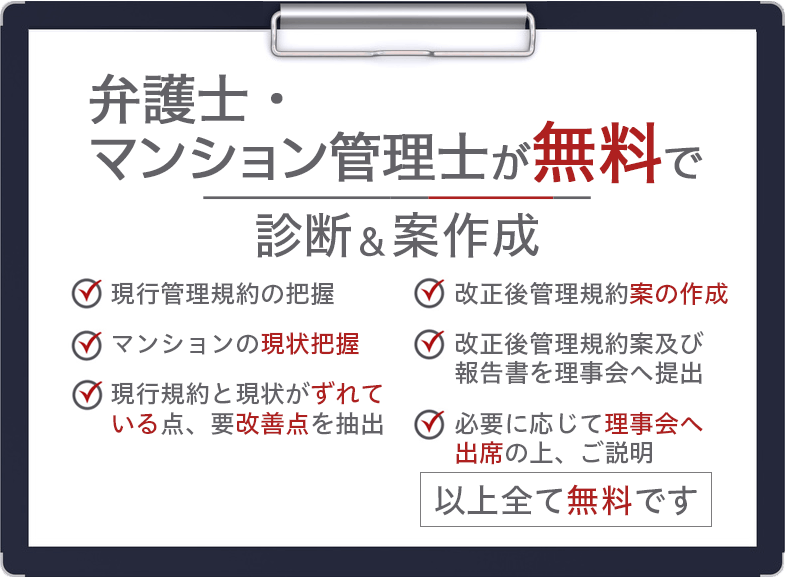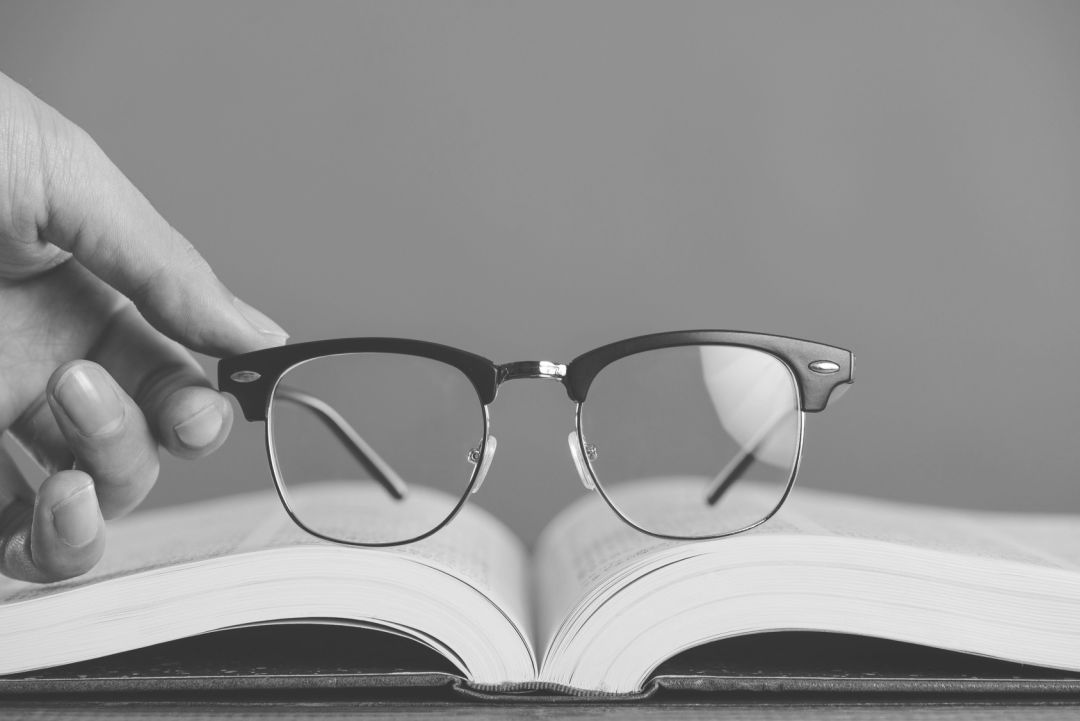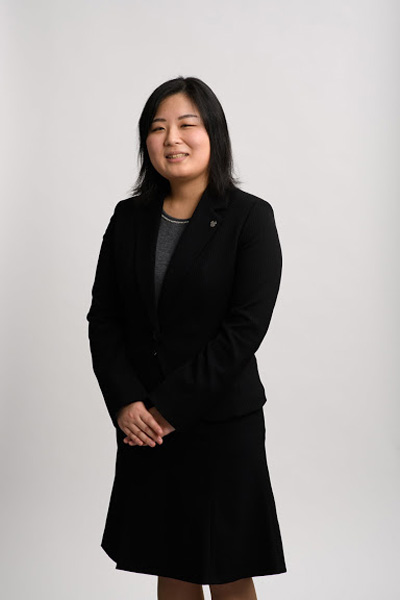弁護士法人サリュ
大阪事務所
〒530-0047
大阪市北区西天満4-8-17 宇治電ビルディング606号
営業時間: 平日10:00-17:00
※年末年始・ゴールデンウィークを除きます。
TEL:06-6130-0117
FAX:06-6130-0118
- 京阪線・御堂筋線「淀屋橋駅」1番出口から徒歩約10分。
- 谷町線・堺筋線「南森町駅」4B または2番出口から徒歩約10分。
- JR線「大阪駅」から徒歩約15分。
- 各線「梅田駅」から徒歩約15分。